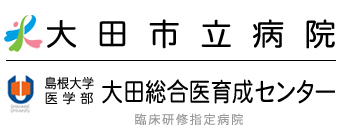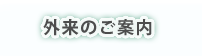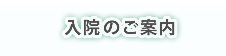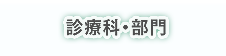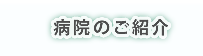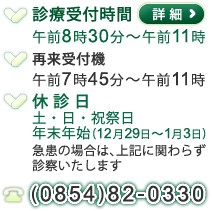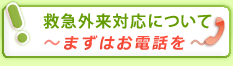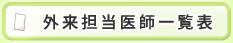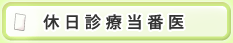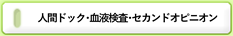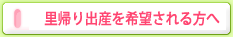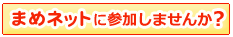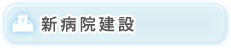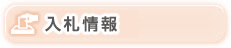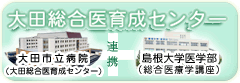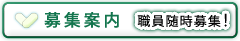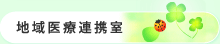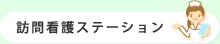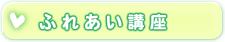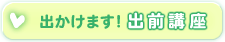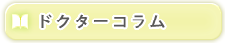H25.7 最近の早期胃がんの内視鏡治療(ESD)と適応について
副院長(消化器科部長)
金藤 英二 医師
近年、早期胃がんに対する内視鏡治療は革新的な技術の進歩を遂げ、外科手術を行わずに治療する早期胃がんの症例が増えています。当院でもこの2年間で約20例程度になっています。
1.EMRとESD
早期胃がんに対する内視鏡治療には、①内視鏡的粘膜切除術(Endoscopic Mucosal Resection, EMR)と、②内視鏡的粘膜下層剥離術(Endoscopic Submucosal Dissection, ESD)の2種類があります。
以前は内視鏡的粘膜切除術( EMR)が技術的に比較的容易なこともあり主に行われていました。しかし、小さな病変でも1回の切除で取りきれないことがあり、治療後の再発の頻度も5-10%程度認めるため、最近では内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)が主に行われています。 ESDは2cmを超える、より大きな病変でも、1回の切除で完全に切除できるので、治療後の再発がほとんどありません。2006年4月からは早期胃がんに対して医療保険の適応となっています。
ESDは、さまざまな処置具を用いて病変の周囲を全周切開し、粘膜下層を剥離することにより病巣部分を一括で切除する治療法です。 従来のEMRと比較すると、病変の範囲を確認しながら切除でき、より大きな病変や潰瘍を合併した病変でも切除が可能です。しかし、その治療手技には高度な技術が必要で、合併症も多いため、正しい知識と正確な技術を身につける必要があります。


2.早期胃がんの内視鏡治療の適応
早期胃がんに対する内視鏡治療は、局所的な治療なので、胃壁外のリンパ節に転移がない病変が対象となります。
―胃がん治療ガイドラインにおける内視鏡治療適応―
<適応の原則>
① リンパ節転移の可能性がほとんどない。
② 腫瘍が一括切除できる大きさ、部位にあること
<絶対適応病変>
① 分化型腺癌
② 2cm以下
③ (肉眼的)粘膜内がん
最近ではESDの技術が進歩し、また多くの外科手術例を検討した結果、リンパ節転移を伴う可能性が極めて低い病変では、2cm以上の病変などにも内視鏡治療の適応が拡大されてきています。
―適応拡大可能となりうる条件―
① 分化型腺癌、粘膜内がん、潰瘍(-),大きさを問わず
② 分化型腺癌、粘膜内がん、潰瘍( ),3cm以下
③ 分化型腺癌、粘膜下層軽度浸潤(SM1)がん、3cm以下
④ 未分化腺癌、粘膜内がん、潰瘍(-),2cm以下
しかし、このような適応拡大した早期胃がんの内視鏡治療は、完全に切除できていないときには外科手術が必要となるため、病変を一括切除し、病理結果を詳しく検討して、完全に切除できたかどうかを判定する必要があります。そのため、ESDでは病変を完全に一括切除することが重要です。
3.内視鏡治療の際の合併症
ESDは高度な技術が必要で、出血や穿孔などの合併症の頻度が高く、合併症の対応に習熟することが不可欠です。
早期胃がんの内視鏡治療は、身体への負担が少ない点からも、今後、高齢者の早期胃がんの治療法としてさらに重要となっていくと思われます。