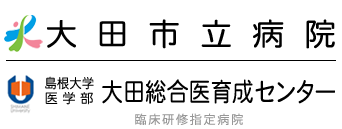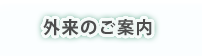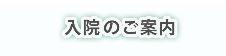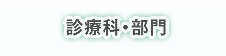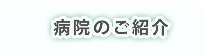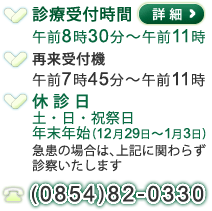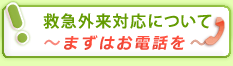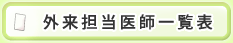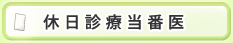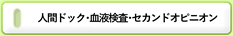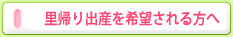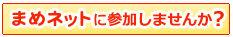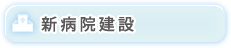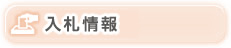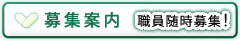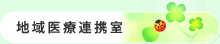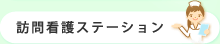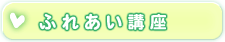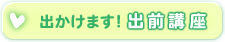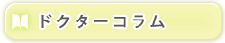第95回 『冬場の健康管理』
まず初めに、私事ながら縁あって大田市立病院に平成19年6月に転勤し、内科診療に携わっていました。
このたび、今年の3月から産休をいただき、5月20日に大田市立病院で女児を無事に出産いたしました。通院中・入院中は主治医の槇原先生、原田先生、看護スタッフのみなさんに温かく支えていただき、休職中には医師不足の中、多くの先生方に大変な支えをいただき、身に余る幸福をかみしめています。
育児休暇を経て、10月より介護療養病棟、リハビリテーション担当として再スタートし、公私ともに充実した毎日を過ごしています。
当院では昨年12月から院内保育所「たんぽぽ」が開設されたことも良いタイミングであり、大変ありがたく思います。現在は登録数が27人、基本保育13人の子供さんが通所され、多くの母親看護師やスタッフの復職の支えとなっています。
大きく脱線してしまいましたがこれから本題に。
秋も深まり、これからはますます寒くなるため、冬場の環境温度と血圧変動についてお話しようと思います。
よく、冬季にトイレやお風呂場で発作が起きて救急搬送されたというお話を聞かれると思います。
加齢とともに、室温低下により血圧が上昇しやすくなり、高血圧症のない人でも収縮期血圧(血圧の高い方の数値といえばピンとくるでしょうか)が160mmhg代まで上昇するというデータがあります。
おおよそ65歳ごろを境に体温調節機能が低下し、急激な体温低下による生理反応も低下して、より危険な状態を引き起こしやすいといわれています。
例えば、一般に加齢とともにトイレに行く回数が増えることが知られています。それに伴って、深夜や早朝にトイレで倒れる例も多く、電気毛布で高温に温められた寝床の中から寒冷な室内(廊下など)に暴露され、脳卒中や心筋梗塞を発症したりします。
また、入浴前に脱衣所で冷えた体が、温かいお風呂場に入る際にも同様な状態となりやすく、住居内での室温の温度差には十分な配慮が必要です。
当院にも、リハビリ室に長い廊下があります。冬場になると寒暖差が生じやすく、利用されるみなさんからも「寒い」とのご指摘がありました。そこで、今年の3月から温度差が生じにくくするため、冷暖房設備を備えました。
みなさんも、冬場に備えて危険箇所を一度チェックされてはいかがでしょうか?
リハビリテーション科医長 岩田 裕子