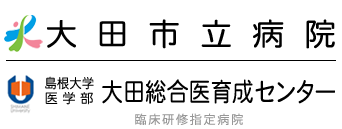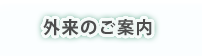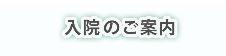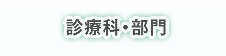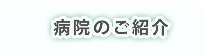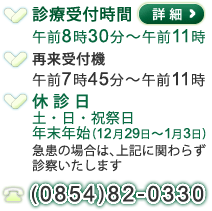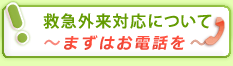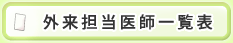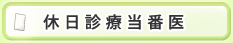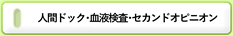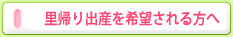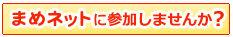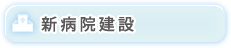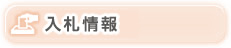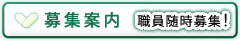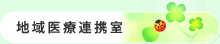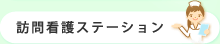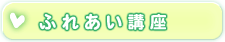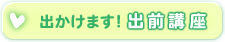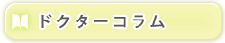第70回 廃用症候群
廃用症候群とは生活不活病、運動不足病とも呼ばれています。
「廃用症候群」。あまり聞き慣れない言葉かと思いますが、病気や障害などにより、安静を保たなければいけないときや、日常の活動性が低下したときに発生する2次的な機能の衰えをいいます。
急性期の医療現場においては、廃用症候群=安静臥床により起こる副作用と考えられます。安静状態が続き、各部分を使用しない状態が続き、各部分を使用しない状態が続くと、本来持っている残存機能が低下しさまざまな障害が発生します。
一般に安静、臥床は病気治療において重要であることはひろく知られておます。
しかしながら安静、臥床には同時にマイナスの面もあります。身体の全部あるいは一部を使用せずにいると(=活動性低下)によって、全身あるいは局所の機能的・形態的障害を生じるのです。
このため、近年、早期離床・早期歩行が大事であるとの認識が医療現場では広がっています。
このように書くと、みなさんは、「病気や怪我で入院したら廃用症候群にならないように注意しよう」と考えられるかもしれません。
しかし、廃用症候群は、病院の中だけで起こることではないのです。廃用症候群は、ささいな風邪などの病気やけがをきっかけとしても容易に起こり得ます。
また病気でなくても、「単なる運動不足」が、身体機能を低下させ、それ自体が身体運動を困難にし、生活の不活発化をまねくという形で、悪循環を形成し新興していくことがあります。特に、高齢者ではおこりやすく、いったんおこると若年層に比べて回復には多大な労力を要します。
運動不足病、生活不活発病とも呼ばれるように、特段の病気の状態でなくても、自宅で不活発に生活しているだけで、自覚のないままゆっくりと進行していくのです。
また、生活の不活発は身体面のみならず精神活動にも影響が現れます。認知機能の低下から物忘れが増える、意欲低下から閉じこもるなどあります。
運動と精神活動には密接な関係があり、運動不足から抑うつ傾向を生じ、逆に運動することにより、うつ傾向の改善が見られるなどの報告もあります。
ほんの数十年前まで、日常生活を維持するには多大な肉体労働が必要で、体を使わずに生活することは不可能でした。
それが、今では、栓を捻るだけで水が出る、スイッチひとつでお風呂のお湯も簡単に準備ができる。洗濯だって洗濯機のボタンを押すだけでできてしまいます。
水道がでない時代には水くみは重労働でした。昔と比較すると、すっかり便利になった現代社会では、日常生活を最低限の活動だけで過ごしていると、それはすなわち運動不足状態なのです。仕事で肉体労働する人意外は、余暇活動などで運動を確保しなければ容易に運動不足に陥ります。
身体(心・精神も)は「使わなければダメ」になっていきます。運動不足かなと多少は気にしているけれど、あまり気に留めずにおられる運動習慣のない方は、これを機会に今の生活スタイルに関して、ぜひ、ご一考くださいませ。
大田市立病院 リハビリテーションセンター医長 福田 理子