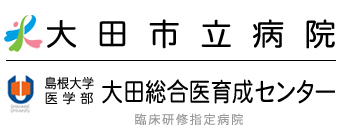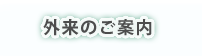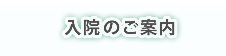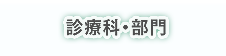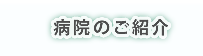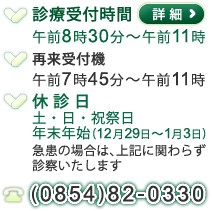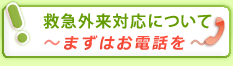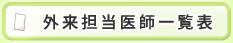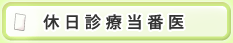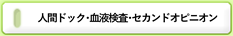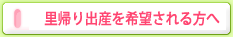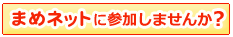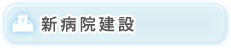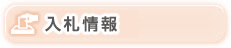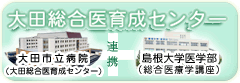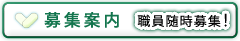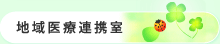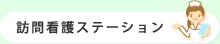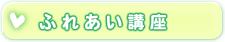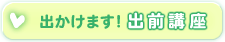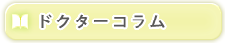第83回 『摂食・嚥下(えんげ)障害について』
みなさんは、嚥下障害に対するリハビリテーションがあることをご存知でしょうか?
健康な状態では、食事をとるという行為は、何気なくあたりまえに毎日繰り返されている日常的な行為となっています。実は嚥下(※)という動作は、神経や筋が精巧に働くことで整然と行なわれている行為であり、これは私たちが生まれてからお乳を飲み始め離乳食を経て少しずつ習得してきたものです。
しかし、何らかの障害により、水や食べ物が飲み込めなくなったり、肺のほうへいってしまうことを「嚥下障害」といいます。また食物が肺へ入ってしまうことを「誤嚥(ごえん)」と呼びます。
嚥下障害になると、栄養失調をおこしたり、肺炎を起こすなど、生命を脅かす事態を引き起こすことがあります。嚥下障害をきたす原因は、
①腫瘍などの術後や炎症により、飲み込む時に使う舌やのどの構造が障害されて起こる場合(例:舌炎、扁桃腺炎、口腔、咽頭腫瘍、食道炎)
②構造物の形には問題がなくても、それを動かす筋肉や神経に障害がある場合(例:脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷、パーキンソン病)
③心理的な要因が関与している場合(例:うつ状態、認知症)
など、大きく分けて3つが挙げられます。
病院での嚥下障害に関するリハビリテーションで一番多くみられるのは脳卒中の患者さんです。
そのほかにも、老化による姿勢の変化による姿勢の変化、虫歯などで歯が減り咀嚼(そしゃく=噛む)力が減少する、唾液の分泌量が低下する、飲み込む筋力や反射が低下する、集中力や注意力が低下するといったことなどから、潜在的に嚥下障害を起こしやすくなるとも言われています。
「肺炎を繰り返す」 「水分でむせる」 「この頃食べるのが遅い」 「体重が減ってきた」 といった状態の見られる場合には、医師に相談しておくことも大切です。
病院では、場合によっては専門的な検査を行なったうえで、その対処方法についての説明や、嚥下体操などを紹介します。また病気の発症などによる重度の嚥下障害の場合には、入院のうえ嚥下リハビリテーションなどを行なうこともあります。
(※「嚥下」(えんげ)とは、モノを飲み込み、胃に送ることを表す言葉です。中国でツバメの子が餌を丸呑みにする様子から、口へんに燕と書いて「飲み込む」という意味になったものです)
大田市立病院リハビリテーション科医長 岩田裕子