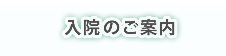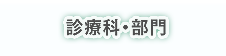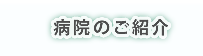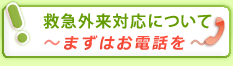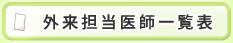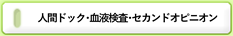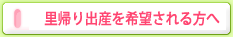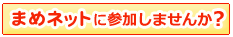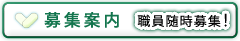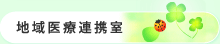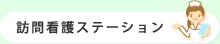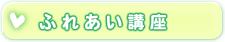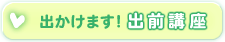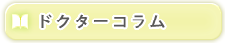第35回 医療と被曝
診療支援部副部長(放射線科) 杉原 正樹
放射線と聞き、みなさんはまず、何を思い浮かべますか。
唯一の被爆国である日本では、やはり原子爆弾やチェルノブイリや東海村の事故などの恐ろしいイメージが、まず思い出されるのではないでしょうか。 その一方で、X線を発見したレントゲンは、第1回ノーベル賞を受賞し、放射性元素を発見・精製したキュリー婦人は2回もノーベル賞を受賞しているように放射線は人類に大きな貢献をしています。実際に現在の医療では、多くの検査・治療に放射線が使用されています。
医療で使われる放射線の量を考える基準として、まず自然放射線について話をしたいと思います。
われわれは人工的に発生させた放射線を浴びなくても、大地や食物、空気に含まれるごく微量の放射性元素、宇宙から地球に降りそそぐ放射線にさらされています。その放射線の量は平均して年間2.4mSv(ミリシーベルト)と言われています。地質によって異なるため、ブラジルのガラバリ市街地では年間10mSvになると言われています。
それに対し、検診で撮影する胸部単純X線検査は0.1mSvです。胃の集団検診を1回受けると大体0.6mSv、精密検査である胸部CTは1回7mSv程になります。 実際に放射線被曝に関わる不安で一番多く相談されるのが、妊娠に関わるものです。
ここで、妊娠中の放射線検査について最近の考え方を説明します。
かつて、女性に放射線検査を行う時は、「十日間規則」が推奨されました。それは、妊娠可能な年代の女性の緊急を要さない検査は、妊娠している可能性のない月経開始から10日間に行なうということです。これは正しいのですが、強調されすぎることで、放射線検査を受けた後で妊娠していることが分かった場合や妊娠していることを言い出せずに検査を受けてしまった場合に、患者さんに強い不安を与えることになり、不必要な中絶が行われるという悲劇をもたらす原因とも指摘されています。
実際には、胎児に対して100mSv未満の被曝では医学的に奇形や精神発達遅滞などの異常は生じません。ですから、胸部や頭部のX線検査など直接胎児に放射線が当たらない検査はむろんのこと、仮に腹部のX線検査など直接胎児に放射線が当たる検査であっても通常の検査であれば、妊娠中絶を考える必要はありません。放射線は量を増やせば、腫瘍を殺したり、脱毛などの強い作用を生体に及ぼします。悪性腫瘍の治療で用いる時の放射線は50~70Sv(50,000~70,000mSv)くらいの量で、先に述べた検査で使用する放射線量の1万倍~10万倍くらいの量なのです。不必要な放射線被曝を避けることは当然のことですが、むやみに放射線を恐れ、不安を抱くことも根拠のないことです。
もし、放射線に関わる疑問、不安がありましたら、放射線技師、放射線科医師にご質問ください。