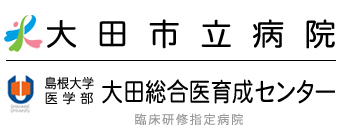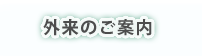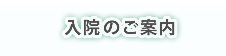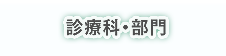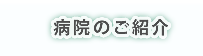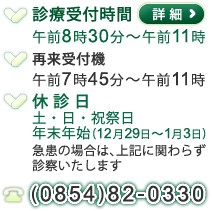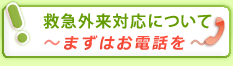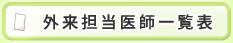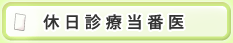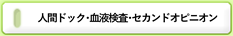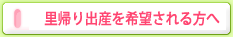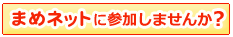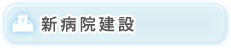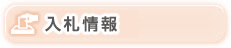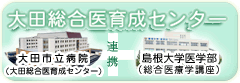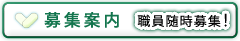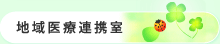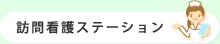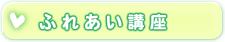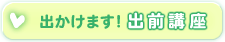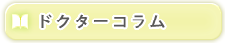第06回 足関節捻挫について
整形外科(外科系診療部長) 内藤 浩平
足関節捻挫(ねんざ)は足関節を構成する骨や軟骨、また靭帯(じんたい)を損傷して痛みや腫れを生じる外傷です。
足首をひねって痛みを生じた経験は、みなさん思い当たることがあると思います。
足関節をひねるとだんだん足首が腫れてきて、どうにも痛くて足をつけなくなってしまうことがあります。ほとんどの方は自宅で湿布を貼り様子をみられるのですが、痛みがひかないために心配になり、この段階で病院を受診されます。
足関節捻挫は、腫れや痛みの部位を確認したあと、エックス線像で足関節の骨折の有無を調べて診断していました。
従来の画像診断ではエックス線撮影を行い、足関節の骨を診ることしかできませんでした。しかし、MRIという画像診断機器の進歩とその画像診断方法の開発により、足関節捻挫の状態をより正確に調べることができるようになっています。
足関節をひねったとき、最も多く損傷する靭帯は前距腓(ぜんきょひ)靭帯で、これまでこの靭帯が断裂しているかどうかを直接調べる方法はありませんでしたが、最近では、MRIを使用してこの靭帯の損傷程度を正確に診断できるようになりました。さらに、MRIで軟骨損傷も調べることができるようになっています。
足関節捻挫の損傷部位を正確に診断できれば、これをもとにより良い治療法を選択できるようになります。また、直径2.7mmの足関節鏡という内視鏡を使用して、関節の内部から骨・軟骨や靭帯の損傷部位を確認したのち内視鏡下の処置を行い、より小さな侵襲で適切な手術ができるような工夫もあります。
足関節を捻挫したあとや骨折したあと、どうも痛みが続くといった症状も同様に、診断・治療が可能ですので、心配な方は当科に相談してみてください。