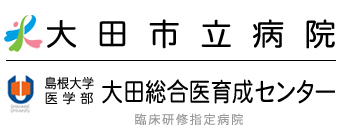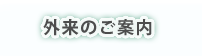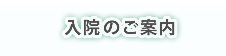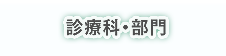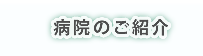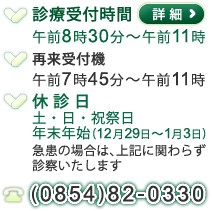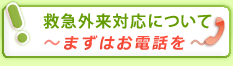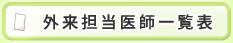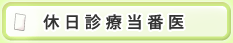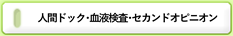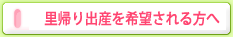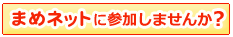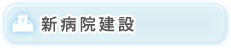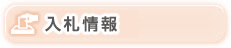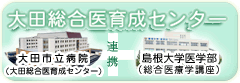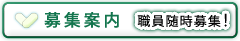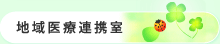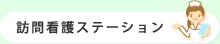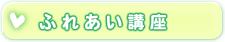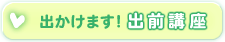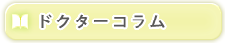第54回 お酒と健康
内科系診療部副部長(内科) 赤木 収ニ
昔から「酒は百薬の長」といわれています。最近の調査・研究でも「適量の飲酒をする人の死亡率が、全く飲まないかあるいは大量飲酒をする人に比べて低い」という報告が数多くされています。
これは、「適量の飲酒は心臓疾患を予防する”善玉”コレステロールを増加させ、”悪玉”コレステロールを低下させるためである」とか、「ストレスを低下させるためである」などと説明されています。
体内に入ったお酒の大部分は、肝臓の酵素でアセトアルデヒドに分解されます。アセトアルデヒドは悪酔いや二日酔いの原因になる物質であり、肝臓で種々の酵素により最終的に、無害な炭酸ガスと水に分解されます。このアセトアルデヒドを分解する酵素の働きが、生まれつき良い人と悪い人があり、これがお酒に強いか弱いかに関係します。日本人の約半数はこの酵素の働きが悪いといわれています。われわれが、お酒を飲んでいい気分になっている時でも、このように肝臓は黙って働き続けています。
しかし、肝臓も絶えずお酒の処理に追われていると、働きが悪くなって肝臓に障害がでてきます。また、肝臓以外にもお酒の飲み過ぎで、脳、心臓、膵臓など全身の臓器に障害を及ぼします。
そのほかにも、「イッキ飲み」などによる死の危険性のある急性アルコール中毒、また妊婦が飲酒することにより胎児に障害を及ぼすことなど、このようにお酒も飲み方を間違えれば、大きな問題をおこします。
しかし、最初に述べたようにお酒は適量を上手に飲めば健康を損なうことなく、むしろ健康にプラスに働くといわれています。適量を超えて毎日飲むと、肝臓やそのほかの臓器に故障を及ぼします。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、よほど悪くならないと症状がでません。ですから、よくお酒を飲む人は定期的に肝臓を中心とした検査をしてもらうことをお勧めします。また、肝臓病だけではなく、そのほかの病気がみつかった場合には、飲酒するかしないかの判断を主治医にしてもらってください。また、すでにほかの病気でお薬を処方してもらっている時も主治医とご相談ください。
最後に、「適量」を守ってお酒と上手につきあって、健康でよりよい生活を続けられることをお祈りします。