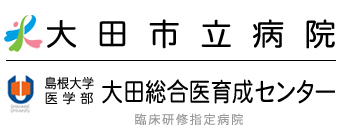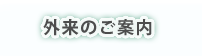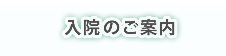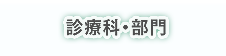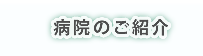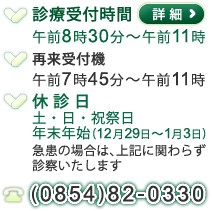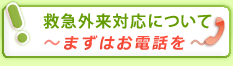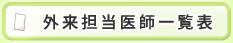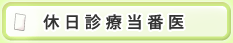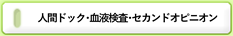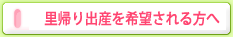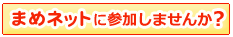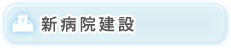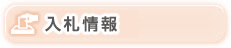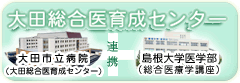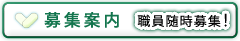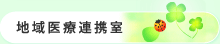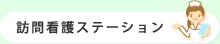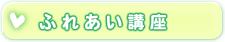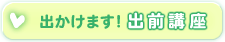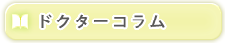第18回 消化器の病気について
消化器科医長 佐藤 宏
消化器の病気は、食習慣、喫煙、飲酒などの生活習慣やストレスとの関わりの強いものが少なくありません。
一例として高脂肪、低繊維化など欧米型の食生活への変化によって、日本人の胃がんは減少し大腸がんが増加しつつあります。また、お酒を何年もの間、たくさん飲めば肝臓の機能障害をきたし、末はアルコール性肝硬変となってしまうこともあります。お酒は肝臓だけでなく、膵臓の働きにも悪影響し、急性あるいは慢性膵炎をひきおこすことが知られています。さらにタバコを多く吸われる方でお酒もたくさん召し上がる方に、食道がんが多い傾向にあるようです。
また、現代のストレス社会を反映して、腹痛や下痢、便秘などの便通の異常を主訴とする過敏性大腸症候群(IBS)や、潰瘍はないのに胃腸が痛むディスペプシア(NUD)という病気が増加してきているといわれています。患者は年々増加し、二十一世紀の現代病になりつつあるといわれてます。
その一方で胃十二指腸潰瘍は細菌感染が原因であることがほぼ明らかとなり、胃の中に住みついたヘリコバクター・ピロリ菌(以下ピロリ菌)というバイ菌に関する研究が盛んに行われています。実際、ピロリ菌を抗生物質で殺す(除菌といいます)と、潰瘍の再発が抑えられるということがわかっています。さらに、興味深いことに、ピロリ菌を除菌すると、将来胃がんになる確率も低くなるという報告が日本の研究者によってなされ、注目されています。
最後に、何の病気でもそうですが、消化器の病気も初期には自覚症状がありません。
そこで、病気の早期発見のためにも積極的に検診を受けていただくようお勧めします。例えば、実際に便潜血反応が陽性で大腸の精密検査を受け、大腸がんと診断される人の確率は0.1~0.2%といわれており、その半数以上は早期がんの状態で発見されるといいます。検診により早期発見さらに早期治療が受けられるようにしたいものです。