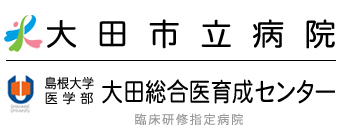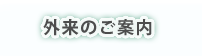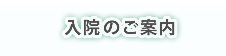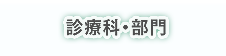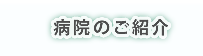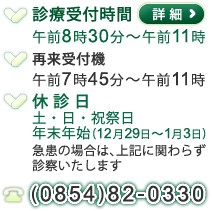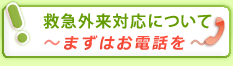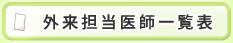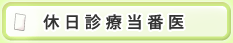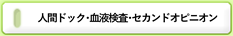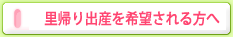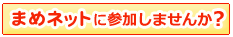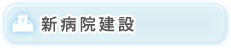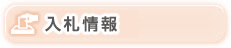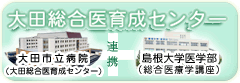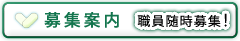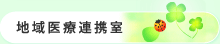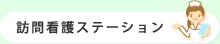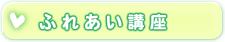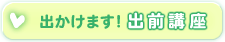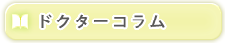第39回 子どもの食生活を改める
小児科医長(診療支援部長) 泉 信夫
私たちの生活はいつの間にかどんどん変わっています。
50年前は、電話は郵便局などでかけていましたし、テレビもまだそれほど普及していませんでした。冷暖房も様変わりし食事も変わってきています。 これらの変化で平均寿命や体格も伸びました。しかし、肥満が増え、子どもの血中脂質の平均は米国の子どものそれを超えてしまいました。今後、心臓や脳血管の怖い病気が増えることが心配です。
肥満と高脂血症は子どもでも多く、対策が検討されています。しかし、成人してからの肥満や高脂血症も多く、さらに、やはり前記の怖い病気の危険因子である高血圧や糖尿病は成人のだれもが成り得ます。肥満児などへの対策は子ども全体の問題と考えます。 肥満、高脂血症、高血圧、糖尿病は一つひとつでは怖い病気の危険度は必ずしも高くなくても、重なると大きく高まります。これらには体質も関与していますが、生活習慣との関わりが切り離せません。
日本人は太古より質素な食事に耐える体質になっています。ここわずか数十年の食生活の変化はあたかも大実験です。嗜好や食生活の基礎は幼小児期に形成されます。
まず、ゆっくりかみ、満腹前に箸を置く習慣です。食事開始から食欲のブレーキのかかり始めまでは約10分は必要です。産地の苦労を想像するなどゆっくり食べる工夫は様々でしょう。
次は薄味の習慣です。日本人の塩分摂取は多くの国の倍以上です。対抗するカリウムを増すためには野菜や果物を多くし、マヨネーズは少なくします。脂肪の過多は現代における食事の最大の問題です。
ただし、魚油は動脈硬化の防御になります。獣肉にかたよらず魚も食べましょう。 現代は砂糖と油でおいしくしかも塩味の利いた「やみつき食品」があまりに手軽になりました。甘味はデザートのように満腹のお腹にも入る魔物です。手軽すぎないような工夫が必要です。
今一度、子どもの食生活を見直してみてください。