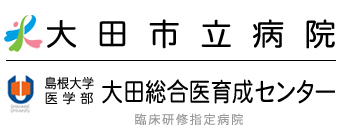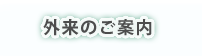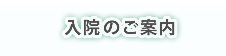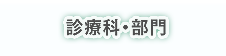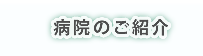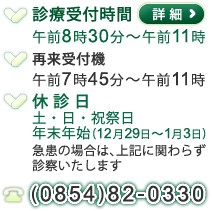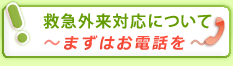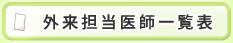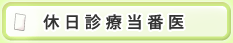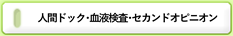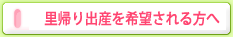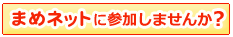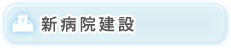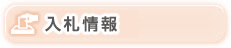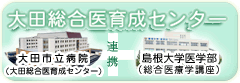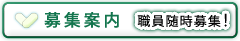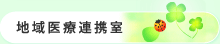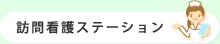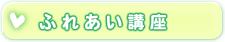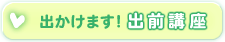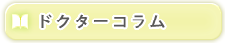第01回 ”痛み”は病気?
麻酔科(副院長) 西尾祐二
これまで医学では『痛みは、体の発する警告信号、病気に付随した一症状であり、原因となった病気が治れば痛みも自然に消失する』と考えられ、痛みそのものの治療は、あまり重要に考えられてきませんでした。
事実、骨折やケガなどの強い痛みでも傷が治ってしまうと、嘘のように無くなってしまうことは多数の人が経験していることです。ところが、”傷が治り検査しても異常がないのに、痛みだけが何故か取れない”ということを経験された方もあることでしょう。
例えば、帯状疱疹(どうまき)の後の痛みや、ケガや手術した後のきずが、梅雨時や寒い日に疼くなどです。いわゆる”古傷が痛む”という状態です。このように発症してから1ヵ月~6ヵ月を経過し、元の原因も治癒したにもかかわらず治らない痛みを慢性痛(神経痛)と言い、治ってしまう痛みと区別します。今まで痛みの慢性化の仕組みはよく分かっていなかったのですが、最近の研究から、ケガなどで切れた神経が、治る過程で配線ミスを生じたり、大量の痛みの信号が脊髄に入ったために、脊髄や脳の神経が変化して、痛みに過敏になったり、痛み以外の刺激も痛みと勘違いするようになることが原因であることが分かってきました。そして、そのような状態が出来上がると通常の鎮痛剤は効かず、治療が難しいことも分かっています。完成した神経痛を治す方法は十分には分かっていません。しかし、痛みの治療を早期から十分に行うことで、かなりの神経痛が予防できることがわかっています。「痛みが出てから1ヵ月経ってもよくならない」「痛みの症状が変わってきた」こういう状況は、痛みが慢性化する兆候です。早い段階で、痛みの専門外来で相談され、神経痛予防対策を立てられるのがよいでしょう。