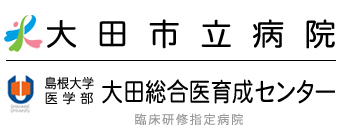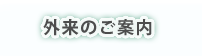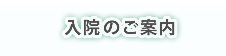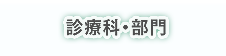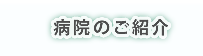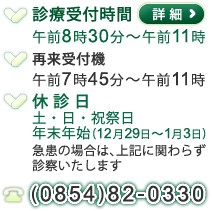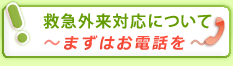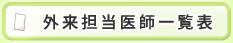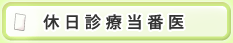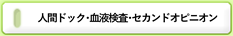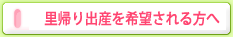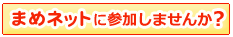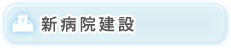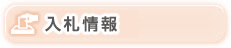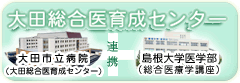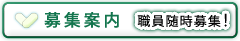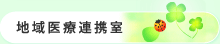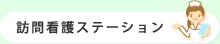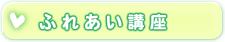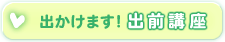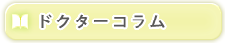第03回 脳卒中のはなし(1)
神経内科(院長) 岡田 和悟
脳卒中とは、「突然悪い風にあたって倒れる」という意味のアポプレキシーというギリシャ語に由来することばであり、それだけ古くから知られていた病気です。
以前は脳卒中になったら安静にするのが第一といわれていた時代もありましたが、CTスキャンやMRI(磁気共鳴装置)などの診断機器の進歩や新しい薬剤の登場、リハビリテーションの普及により、病気への対応が変わってきています。
これから3回にわたり最近の脳卒中に関する診断や治療について分かり易く説明したいと思います。
脳卒中とは、別名、脳血管障害とも呼ばれ、その名のように脳へ血液を送る血管がつまったり(閉塞)、破れたりして起こる病気です。
血管がつまる場合を脳梗塞と呼び、動脈硬化が原因であるアテローム血栓性脳梗塞と心臓などから血のかたまりが飛んで起こる脳塞栓症および細い血管の閉塞によるラクナ梗塞があります。
脳へ行く血管が破れる病気としては、脳の中の血管が破れる脳内出血と脳の外の血管のこぶ(動脈瘤)が破れるくも膜下出血があります。
最近の日本全国での脳卒中は、死亡原因では悪性腫瘍に次いで第2位であり、年間人口10万人当たり120人程度が脳卒中で亡くなり、死亡総数の16%にあたります。入院の原因としても第2位で、長く入院を必要とする方も多くみられます。更に問題になるのは、寝たきりや介護保険対象者の病気のうちほぼ半数を占めていることです。
脳卒中の症状としては、障害をうける脳の部位により、意識障害、運動障害(半身が動かなくなる)、感覚障害(半身の感覚が鈍くなる)、平衡障害(ふらつき)、けいれん(大脳皮質が障害をうけた場合)、視野障害(後頭部が障害をうけた場合)、視力障害(眼の動脈が詰まった場合)、頭痛(出血した場合)、痴呆(多発性の脳卒中の場合)などがあります。症状としては、運動障害(片麻痺)が最も多くみられます。
これらの脳卒中発作のまえぶれとしての症状に、一過性脳虚血発作(TIA)と呼ばれる状態があります。この状態は先ほど述べた脳卒中の症状が、24時間以内(多くは数分以内)に消失する状態をさします。
首の部分の動脈(頚動脈)にできた病巣から小さな血液のかたまりがはがれて、脳の細い血管につまり、それが自然に溶けて症状がなくなる状態とされています。この状態になると、1年以内に、20~30%の方が脳梗塞になるとされています。
高血圧や糖尿病、高脂血症、心臓病などを患っていてこのような症状がみられたら、信号が黄色になった状態と考えて、早めに医療機関で受診し、検査や治療を受けることが大事です。
次回は、脳卒中の症状と検査について説明する予定です。